また今日もアイス食べたいなる子です。
先日、スイカ割りがリスク高すぎ、と言う記事を書きました。
今日は怪談話を子どもたちにするのはリスク高すぎ問題を取り上げたいと思います。
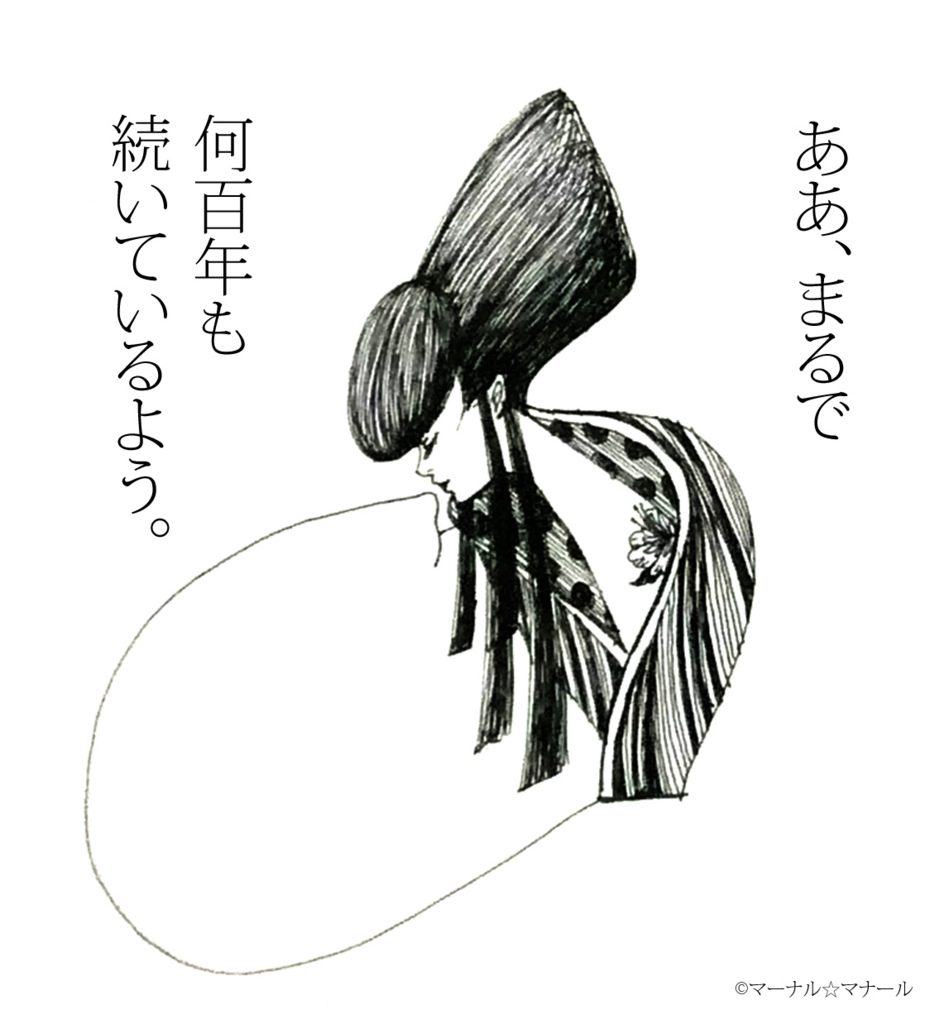
お化けは夏のお楽しみ
先に言っときますけど、基本的にお化け好きな子は多いです。
テレビでも怪談ものが増えるせいか、夏になるとお化け屋敷ごっことか、ゾンビごっことか、貞子ごっことか、謎の遊びが増えます。
(あ、そういえばハロウィンでレベルの低い貞子コスプレしたことあります。髪の毛が長かったから。)
大人にも怖い話をねだります。
「怖い話して!」
「もっと!」
本当に話すと、ちょっとビビってるくせに
「全然怖くないし。」
と、いきがって見せます。
かわいいねえ。
怖い話は自粛!
子育て系の施設で、怪談話は自粛傾向にあります。
本当にトラウマになる子がいるからです。
保育園とか節分で鬼のお面かぶるだけで泣きますからね。
「うちの子が眠れなくなった!」と言うクレームがくることも。
小学生でも?と思うでしょう?
小学生でも「青くてでかいのと緑の目玉のCGアニメ映画」怖くて見れない子いますからね。
あれって怖い話でしたっけ?ハートフルじゃない?でもこれ、マジな話です。
集団に怖い話を聞かせるようなことは、大勢にとってエンターテイメントでも、ある子にとっては恐怖のドン底に突き落とされるような経験なのです。しかも逃げられないなんて…!
要は半強制的に参加させるような怪談話はNGってことです。
嫌だな、と思えば最初から参加しなくていいし、途中で抜けるのもOK。そういう仕組みを事前に作っておけば大丈夫。
そして、本当に本当に本当に怖い話はしない。
「全然怖くないし」
って言ってられるぐらいにセーブします。
子どもは物語を通して、いろいろな感情を経験し成長する
今や、日本の子どもたちにとって、物語を通して経験する生まれて初めての恐怖ってこの本なんじゃないかと思います。せなけいこさん作「ねないこ だれだ」
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16ede23d.cecd089e.16ede23e.9ee9f955/?me_id=1213310&item_id=10170844&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2188%2F9784834002188.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2188%2F9784834002188.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
ねないこだれだ (いやだいやだの絵本) [ せなけいこ ]
|
衝撃のラスト。
天使のような赤ちゃんに、こんな本読んでいいのか不安になりますが、ちっちゃな子どもたちに大人気で、「もーいっかい!」の常連です。
ちょっと怖いんだけど、何度も「怖い」を経験する事で、ひとつ、「怖い」を克服していくことができるんだと思います。
にこにこ笑っていることだけが人間の感情ではなく、もっと複雑だし、感情を経験することは子どもたちにとって成長なのです。
3.11の地震の後、被災地の子どもたちが「地震・津波ごっこ」を始めて大人がギョッとする、というような事が話題になりました。
専門家の人が「安全が確保された時に出てくる遊び。子どもたちの自己治癒力。」というようなことを言ってたと思います。
安全なところにいるから(お母さんや信頼している先生がいる場所)怖いものを安心して経験できるのですね。
貞子ごっこも怖いものを克服する手段なのかも。
怖い話はやっぱり楽しい
楽しいからさ。話したくなっちゃう。
怖がりの子は別室でお過ごしください。
もしくはお話聞きたい人は個別対応いたします。
私の恐怖体験は。。。
また来年のベストシーズンになった時に記事が書けるよう温存しとこうっと☆
